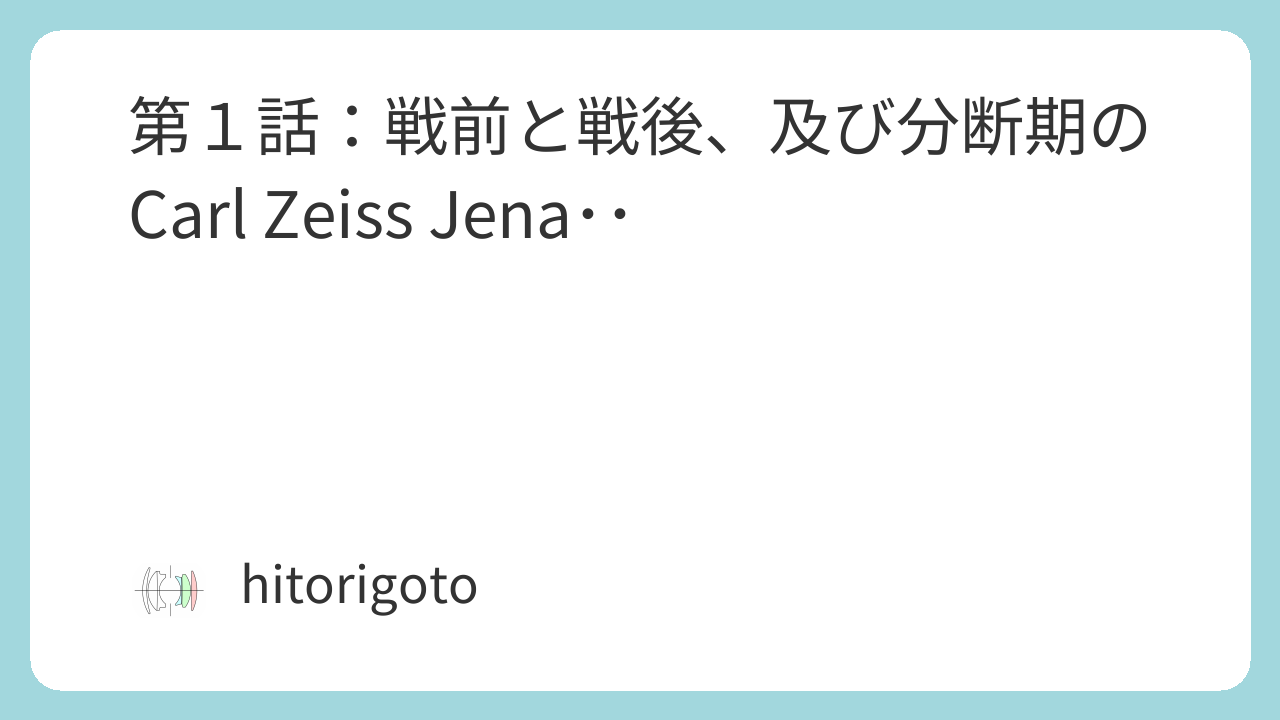🅰
ひと言に「Carl Zeiss Jena (カールツァイス・イエナ)」と言っても、実は戦前ドイツでのCarl Zeiss Jenaを指す話なのか、戦後に旧東西ドイツに国が分断されてしまっている中での話なのか、それらを正しく認識しながら捉えないと、話の内容が真っすぐ進んでいないことになります(汗)
つまり「Carl Zeiss Jena (戦前)」と「Carl Zeiss Jena (旧東ドイツ時代)」さらに「Carl Zeiss (旧西ドイツ時代)」そして1990年10月3日以降の「Carl Zeiss (再統一後の現在のドイツ)」と言う4つの認識が存在する光学メーカー名であることを知る必要があります。
この時、4つめの旧東西ドイツ再統一後の「Carl Ziss」には、旧東ドイツの「Carl Zeiss Jena」が吸収合併されています。
多くの場合で「Cael Zeiss Jena」を語る時、戦前を指しているのか旧東ドイツ時代なのかの別は、残念ながらちゃんと明確化して語られないことが多く、それらの認知は文脈を通して理解するしか手がありません(泣)
またそれら詳細を知っている人の中には、旧東ドイツ時代の「Carl Zeiss Jena」を指して単に「DDR」或いは「Carl Zeiss Jena DDR」と表記する場合もあります。その一方で旧西ドイツ側「Carl Zeiss」を指して「oberkochen (オーバーコッヘン)」と表記する人もいます。
それぞれでちゃんと意味がある表記、或いは使い方なのですが、実はこれらの表現は「全てオールドレンズの範疇に限定して語っているつもりになっている」ことが多いのです(汗)
確かにこの当時のオールドレンズの中で「CARL ZEISS JENA DDR」と鏡胴に赤色で刻印してある個体が今も市場流通しています。しかし実は全ての旧東ドイツ時代に製産されていた「Carl Zeiss Jena」製オールドレンズの個体に、必ずその同じ鏡胴刻印が残されていたワケではないのです(汗)
実際、今現在も市場流通している「Carl Zeiss Jena」製オールドレンズの個体の多くは、刻印があったりなかったりバラバラです。さらに鏡胴刻印ではなく、そもそもレンズ銘板のブランド銘刻印が「Carl Zeiss Jena」ではなく「CARL ZEISS JENA DDR」或いは「aus JENA」や「C. Z. Jena」だったりする個体まで流れています(汗)
すると今度は「時代とともに呼称が変わっていった」と説明して済ませてしまっているサイトまで現れます(汗)
このような現状のバックボーンから「何だかよく分からないが、きっと旧東ドイツ時代の個体だろう」との受け取りで認識されている話だったりします(笑)・・それはもちろん、実際にそのモデルバリエーションまで辿ってみれば、間違いなく旧東ドイツ時代の「Carl Zeiss Jena」製オールドレンズなのが確定します。
先ずは、ネット上で頻繁に語られている「旧東ドイツ時代のCarl Zeiss Jenaの歴史の話」以前に、そもそも前述してきた話の認識が正しいのか、或いは適切な表記として通用すべき範疇が適合しているのかについて、理解を深める必要があるのです(汗)
戦前戦後の、或いは旧東西ドイツ内での「Carl Zeiss Jena」や「Carl Zeiss」の光学メーカー銘の違いや歴史にその変遷を語るのは・・・・実はそれからの話になるべきなのです!
(多くのサイトでそれを蔑ろにし続けているから、ちゃんとした理解が促されない)
特に今ドキのサクッと説明を進めるサイトの定型フォーマットにハマると、余計にそのようなパターン化が流行り、あっという間に結論として「まとめ」に仕上げられてしまいます(笑)
………………………………………………………………………………………
先ず一つの大前提として、先に指摘しておく事柄があります・・それは「旧東西ドイツ」と言う呼び方、或いは国の呼称 (通称) についての正しい認識です。
先に戦前ドイツでの「Carl Zeiss Jena」の歴史などについて話を進めてしまう前に、敢えて戦後世界での認知を今一度確実に理解する必要があるのです (実は、それによって戦前の受け取り方まで変わってしまうから)。
或る意味、この点をシッカリ明確に、先に説明しているサイトがあまりにも少なすぎるが故に、不必要な混乱を招いていると指摘できます。
戦前ドイツは誰が何と言おうとも「一つの独立国家」でした。ところが第二次世界大戦の敗戦によって戦後ドイツは大きく変化します・・皆さんご存知のとおり「東西ドイツに分断されてしまった」からですね(涙)
ところが実はこの分断で国が東西に分かれたままを指して「国家として承認していた」と受け取ってしまう風潮が、あまりにも多すぎるから話しを複雑にしています(汗)
旧東ドイツは「ドイツ民主共和国 (Deutsche Demokratische Republik)」なのでその略語は「DDR」になりますが、実はこれはドイツ語表記された時の通称です。
旧東ドイツのラテン語/英語表記は「同じドイツ民主共和国にしても (German Democratic Republic)」ですから、その場合の通称は正しくは「GDR」になります。
つまりドイツ語表記とラテン語/英語表記とで「DDR/GDR」の別が分かれていることを、多くの人達が認識していませんし (特に英語圏に属さないニッポン人に多い話)、もっと言うならいずれも国家ではないので輸出入に係る『通称』なのです(汗)
するとこの時、前述した「CARL ZEISS JENA DDR」はレンズ銘板の刻印だろうが鏡胴だろうが関係なく「ドイツ語で表記していた製造メーカー銘」を表していると理解できるのです(汗)
そこでさらにもっと深く研究を進めます・・この時に合わせて「国外輸出」つまり旧東ドイツから他国にその製品を輸出したらどうなるのかについて考えます。
何故なら、当時の国際輸出入管理法 (正式名称は外国為替及び外国貿易法/いわゆる外為法) の法律では「製造国名を製品にラテン語/英語で表記する義務を課す」としていたのです(汗)
・・いわゆる「LENS MADE IN どこそこ」と言う刻印ですね(笑) だからこそ様々な製品にラテン語/英語で今現在も刻印されているのです。
つまり前述「CARL ZIESS JENA DDR」はドイツ語表記なので、その法律に違反している製品になってしまいます(汗)・・結果、旧東ドイツから輸出される製品は「CARL ZEISS JENA GDR」との表記が国際輸出入法に則った製造国名表記になるのですが、リアルな現実はそのような個体数は圧倒的に少ないのです(涙)
そしてその理由や背景を調べていくと、もっと本質的、且つ根本的な問題点に突き当たりました!
(旧) 東ドイツも (旧) 西ドイツも、国際法では正式な国家として承認されていなかったのです(汗)
それはそうです、そもそも第二次世界大戦集結の際、戦前ドイツの戦後処理の中で「連合国によって占領統治された戦後処理のスタートだったのが東西ドイツ分断の開始点」であることまでちゃんと考えれば、その道理はまさに史実が語っているワケで、納得するしかありません(汗)
そこで複雑化に至ってしまったのが、連合国 (軍) の中に「旧ソビエト連邦 (通称ソ連)」が含まれていた点です。
結果、戦後は旧ソ連が占領統治する「 (旧) 東ドイツ」と、一方でアメリカ・イギリス・フランスによって占領統治されたのが「 (旧) 西ドイツ」と言うのが正しい認識です。
ネット上の解説で誰一人例えて述べませんが、仮に私達が住まうこの日本で、敗戦時に東日本 (旧ソ連占領統治) と西日本 (米英仏占領統治) の2つに、糸魚川を境にして国が分断されたままに戦後が進んでいたとしたら、その時ニッポン人はそれぞれの国を認めてほしいと考えていたでしょうか???
それぞれを指して「東日本国/西日本国」に承認すべく世界に主張していたでしょうか・・(汗)
そこにまさに当時のドイツ人、ひいては現在のドイツ人が指摘する「もとは1つの国だったんだ」との主張に、当方的にはとても強く納得感、共感を覚えるのです(汗)
ここで先の説明の中で『通称』と表記したのには理由があり、国際法上は戦後ドイツの占領統治時代の分断期を指して「国家認証していない」のが正しく、それはまさにそのコトバのとおり占領統治していたからです (そもそも国家云々を語れる状況にない/第三国に占領されている状態だから)。
それは真に法律理論で捉えるなら、おそらくは旧東西ドイツの国民それぞれが、国民投票によってのみ各国の独立宣言を世界に主張しない限り、認められないのではないかとも考えるのです(汗)
(戦勝国だからと言っても、勝手に占領国の独立とその分割を宣言できない)
それこそ今で言う処のウクライナ東部州で、国民投票まで行ってロシアへの編入を (ポーズ的に) 執っているロシアのヤリ様などが該当する話とも指摘できそうです(既に独立した国の領土をいきなり侵略し、勝手に自国領土に編入する概念を認めるべきなのか)(汗)
「占領統治」と言うコトバには、そのような重みを伴うと、強く、本当に強く思うのです。
従ってこの「占領統治」と言うコトバに純粋に「戦勝国が占領して統治したから」と充てがって済まそうとするから余計に話が複雑化します(汗)・・これも正しくは「戦時賠償 (戦後賠償ではない)」の一環として占領統治したのが正しい受け取りであって、単純に戦勝国が占領統治したと言う説明や表現にまとめてしまう考え方は、少々乱暴すぎないかと言う話をしています(汗)
これは同じ敗戦国の日本の状況に重ね合わせるとよ〜く分かります。ドイツ敗戦は1945年5月7日の米英仏連合国軍との降伏文章調印、及び1945年5月9日旧ソ連軍との降伏文章調印によって決定し、一方の日本は1945年8月14日のポツダム宣言受諾 (玉音放送に拠る日本国民への周知徹底は翌日8月15日正午) です。
ここで着目すべきはたった一つしかありません「降伏時に政府が機能していたのか???」であって、降伏文章調印はその次の話です。
敗戦ドイツは無政府状態にあり機能していませんでした (あくまでも臨時政府が急遽用意されただけの話)。一方日本は戦時下にしても政府が正しく機能していた状況にあり、この差が「戦勝国にとっての戦時賠償問題の大きな格差を生んだ」というのが歴史的事実です。
つまり互いに敗戦国ながら、また首都含め爆撃を受けており、国内の主だった産業工業経済面での打撃は計り知れなかったにしても、政府が機能していた点で日本の占領統治はドイツとはまるで違う趣きを成しまた。即座に戦時賠償問題にとりかかれたのです。この結果、同じように分割統治を主張した旧ソ連を説得した米英仏によって米国単独に拠る占領統治が決まりました。
ちなみに「戦後賠償」は、戦争被害者 (個人や団体) に対する賠償問題 (戦争加害国が支払う補償や救済) を指すのであって、まるで趣旨が違います。
これは特に戦後賠償を自ら政府自身が率先して行った同じ敗戦国の日本とは、戦後ドイツ、或いは再統一後のドイツはまるで違っており、正直な話、いまだにドイツは戦後賠償していません (一部団体に拠るユダヤ人問題での戦後賠償は顕在しますが、国としての戦後賠償は未実施です)(汗)
そもそも戦後に国が分断されたことから国家としての戦後賠償未実施たる根拠にあて、且つその分断期の期間は前述のとおり戦時賠償を目的にしていたことを俎上に挙げて、必然的に戦後賠償にも資するとしたのが再統一後の現在のドイツの言い分です。
それはそうです。占領統治下の期間で、互いの国での産業工業経済のあらゆる分野で戦時賠償が続けられてきたとすれば (実際、敗戦時の戦後賠償対価に比した時、ドイツ再統一時点の賠償額は既に5倍以上に達していた) 十分戦後賠償の対価すら旧東西ドイツ国民から搾取していたことを否定できないのです(涙)
その意味で、一部の国が今現在も日本の戦後賠償問題の未実施/未完了を盾にして、国連に申し立てている事実は、真に以て不適切だとしか言いようがないのです (ドイツは既に謝罪したと言うが、それは決して戦後賠償の話にイコールではない)(笑)
これは日本の戦後賠償問題でも同じように、終戦時の取り決めよりも多く支払っていると欧米諸国間で語られていますが、そもそも戦後の旧東西ドイツ国民の話だけに限定せず、日本ですら国民から長年搾取され続けてきたことを意味するワケで、何をか言わんやと言う話です (実際中国にも韓国にも必要額全額を既に時の政権に対し支払い、賠償し終わっているにもかかわらず、さらにODA (政府開発援助) として別の手段でそれらの国々に継続支援を長年続けてきました)(汗)
・・何と中国に対しては、2021年末時点でようやく全てのODAが完遂しています。
そうやって技術支援しつつも、実のところ技術は漏洩していったワケで、挙句の果てが今現在の中国の国力と言う話です(涙)・・然しこの時、自国 (つまり日本) も同時に中国を利用/活用しつつ自国経済と国力発展に導いていったのは間違いないワケで、なかなかに、なかなかに考えさせられます(泣)
この趣旨の違いは、例えば現在で言うところのジュネーブ条約下にある「国際人道法」の概念の使い方と、まるで似ています(汗)
はたしてその「人道」と言うコトバは、国連で承認されているいくつかの法典に照らしているコトバなのか (実際それは “人権” を指す)、或いは「武力紛争当事国間での人道的配慮を定めた国際法の話」なのかを明確に捉えないまま使っていることが多いのも事実なのです(汗)・・この時「人道」と言うコトバは、後者の武力紛争状態にある国同士を対象にして使うべきコトバであることを、例えば自衛隊幹部ならちゃんと認識しています。
・・つまり「人権≠人道」と認識するべきなのです。
だからこそ、今現在のガザ地区でのパレスチナ人困窮状態に対し、国連の「人道支援」が騒がれているワケで、そこに「人権」をあてがうのは戦争犯罪に対する内容だけになるのです。
話を戻して、戦時賠償の一環として占領統治した結果の旧東西ドイツ分断が概念の根本を成す為、それらは国際法上は「国家としての認識に値しない」のが道理なのです。しかしそうは言っても当時の輸出入上で様々な問題を引き起こすので「通念上、国家に該当する通称使用とする」として認められた (附則が) 当時の国際輸出入管理法の話だったのです。
従って旧東西ドイツの呼称は、輸出入管理面での通称使用であって、決して国家名称ではないことを認知するべきですね(汗)
………………………………………………………………………………………
ここまで来てようやく旧東西ドイツに関する国家呼称の真の捉え方が明白になりました。
ここで例えばシルバー鏡胴時代の「Carl Zeiss Jena」製オールドレンズで「Biotar 58mm f/2 T」と言うモデルをピックアップして説明してみたいと思います (敢えてT刻印無しのBiotar 5.8cm f/2のほうを例に挙げません)。
 このシルバー鏡胴時代のBiotarですら、実は鏡胴刻印に「Germany」が刻まれていたり、何も製造国表記が無かったりとバラバラです(笑)
このシルバー鏡胴時代のBiotarですら、実は鏡胴刻印に「Germany」が刻まれていたり、何も製造国表記が無かったりとバラバラです(笑)
左写真では鏡胴のマウント部直前に「Germany」刻印が見えています (写真左端に微かに見えている)。すると左写真の個体はモデルバリエーション上では「中期型−I」にあたる為、戦前〜戦時中ドイツで製産されていた個体の一つだと受け取れるのです。
そして上の左写真のレンズ銘板をチェックした時、実は「zeissのT」刻印が附随する為、この「T」刻印はモノコーティングを表すことから、当時の戦前ドイツでシングルコーティング (単層膜蒸着コーティング層) が開発された1935年以降、1939年にモノコーティング (複層膜蒸着コーティング層) が開発された経緯を知れば、少なくとも1939年以降の製産個体だとの信憑性すら高くなるのです(汗)
従って鏡胴に刻印されている「Germany」刻印は、戦後の東西ドイツ分断期以前の製産個体を示す「証拠」とも指摘でき、且つそのラテン語/英語表記から (戦前期に於けるドイツ国名のドイツ語表記は Deutsches Reich を継承していた為)、この個体が戦前の欧米諸国向け輸出個体だったことが確定するのです (枢軸国圏向けの輸出個体には、慣例的に製造国表記が省かれていた)。たかが鏡胴の刻印一つだけでその個体が辿った僅かな足跡すら辿るチャンスに遭遇できるのです(涙)
またレンズ銘板の「Carl Zeiss Jena」刻印も、まさに戦前〜戦中ドイツ国内での本家本元「Carl Zeiss Jena」であったことも、ここまでの解説でより信憑性の高い確定事項として納得できるようになるのではないでしょうか。
何故なら、戦後の旧東西ドイツに於ける旧東ドイツ側「Carl Zeiss Jena」と、旧西ドイツ側「Carl Zeiss」との「Carl Zeiss銘」をかけた商標権問題は、戦後すぐに互いの主張によりその問題が表面化し、最終的に権利証や確保人材 (接収した人材のこと) を拠り所として、旧西ドイツ側「Carl Zeiss」が権利を主張し、特に西側諸国向けへの輸出に際し旧東ドイツ側「Carl Zeiss Jena」に対して「Carl Zeiss銘の使用を禁ずる」制限を課したことに端を発します(泣)
実際それを拠り所にして、1953年に商標権裁判を旧東ドイツ側「Carl Zeiss Jena」が国際司法裁判所 (ロンドン) に提訴するものの、凡そ18年にも及ぶ長大な審理期間を経て1970年にようやく結審し、翌年1971年4月26日に旧西ドイツ側「Carl Zeiss」が勝訴しています。
(つまりoberkochenのCarl Zeissが勝訴した)
そこで審理期間中に考え出されたのが折衷案であって (何故なら旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaには、権利主張を確定し決定づける権利証が無かったから/但し史実として戦前ドイツ時代からのCarl Zeiss Jenaの存続が継承されていた事実も認められる/合わせて審理期間中に製品の輸出を互いに停止できない)、旧東ドイツ側の「Cale Zeiss Jena」が「aus JENA」或いは後に「C. Z. Jena」をレンズ銘板に刻印するようになりました (ここで言う “aus” は、ドイツ語表記なので “〜製” の意味合いを含みますから自国内と東欧圏向け輸出品を指し、西欧圏向け輸出品に限り “C. Z. Jena” を刻印していたことになります)・・裁判後の制約とはまた別の折衷案であり、審理中の18年間の中で徐々に変わっていった互いの輸出入ルールの内容です。
一方判決後には新たなルールが適用され、それは最終的に1989年11月の「ベルリンの壁崩壊事件」勃発まで、旧東ドイツ側Carl Zeiss Jenaを苦しめ続ける要素になっていました。
戦後の分断以降からすぐに始まった、旧ソ連から下される「産業工業5カ年計画」履行の中で、光学精密機械VVB (省庁直下の局) として、傘下の取りまとめ役筆頭ポジションに就いたピーク時のCarl Zeiss Jenaは、その従業員数が44,000人だったのに対し (1968年時点)、1989年時点は77,000人を優に超えていたことからも、如何に巨大化していたのかが窺えます。
最終的にドイツ再統一直前のCarl Zeiss Jenaは、長年直下に従わせていた「PENTACON (ペンタコン)」すら既に吸収合併し、もはや旧東ドイツで競合が存在しない巨大企業にまで膨張していたことが分かるのです。
これらの事柄から、ドイツ語表記なのかラテン語/英語表記なのかの相違、或いは刻印の内容、そしてまさに史実の中での商標権問題を抱えて様々な製品を互いに出荷しあっていたことを知ることになります(汗)
ちなみに今現在の市場動向で流通個体をチェックしても「明らかにドイツ語表記のほうの個体数のほうが圧倒的に多い」現実に、はたして西側陣営への輸出が機能していたのかとの疑念しか残りません(汗)
この点についてはだいぶ昔にネット上の研究論文や、ギリシャのディーラーから直接聞き得た情報として、実のところ分断期に「Interzonenzug (ドイツ領域通貨列車)」で旧東ドイツ内に位置する旧東ベルリンの機関車用操車場内で、東欧圏向け輸出品の通関処理後の積替え作業 (密輸) が頻発していたことを知りました(汗) 操車場で積替え作業していた理由は、純粋に旧東ドイツ内の鉄道が複線化できていなかったことに起因します。
それはそうです。Carl Zeiss側の制約だけに依存していた輸出量では、とても従業員を賄えなかったことは想像に難くなく、まさにその結果が現在の市場流通品の中でのドイツ語表記 (DDR) の個体数が圧倒的に多い根拠のような気にもなってきます(汗)
その意味でも、このような「刻印文字の表記」に着目して捉えることで、リアルな現実たる流通状況との照合の中で、その矛盾点として俎上に挙げるのもアリではないかと・・思うのです(汗)
………………………………………………………………………………………
如何ですか??? 国家としての『通称使用』にドイツ語表記とラテン語/英語に係る「国際輸出入管理法から捉えた」認識、そして国が占領統治によって分断されてしまったことに起因する「商標権問題」と、いくつもの課題を抱えながらも、実は連綿に淡々と、そして粛々とオールドレンズ達が製産されて世界中を駆け巡っていたことを・・別の着眼点の角度から眺めることで、逆により具体性が増して納得感に繋がっていく道筋を辿れました(笑)
このような経緯やルートを辿ることこそがオールドレンズに対するより深い慈しみの想いを増長させる機会を得られることを意味し、大のお気にのオールドレンズへの眼差しも、またより一層強く和やかに微笑ましく変わるのではないでしょうか・・。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
それではいよいよ旧東ドイツ国内での「Carl Zeiss Jena」のポジショニングとその変遷について語っていくことになりますが、先にサクッと戦前ドイツ国内での歴史から述べていきます。
※現在まだまだ執筆中・・です (スミマセン)(汗)
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
先に1945年のドイツ降伏時の中で、やはり特に注目すべき「Carl Zeiss Jenaの工場の状況」について述べたいと思います。
Carl Zeiss Jenaの工場施設群が建てられていた場所は、ベルリンの南西方向250kmに位置する、Thüringen (テューリンゲン) 州Jena市であり「Jena (イエーナではなくイエナです)」が地名であることを意味しています (つまりイエナのカールツァイスと言うのが名称)。
従って上のほうで解説した輸出時の制約の中で「aus JENA (アウス・イエナ)」が「イエナ製」を語るだけで、カール・ツァイス製を表していた根拠とも言えます。
そしてそのCarl Zeiss Jenaの工場施設群には工場の機械設備はもちろん、科学者や設計技師に職員や従業員、果ては「戦時徴用兵」とは名ばかりの、民間人労役者 (3,899人) などが住まう地域であり、凡そ当時の関係者総数は1万3千人程度と見積もられています。
そこに終戦間際のタイミングで米軍が侵攻してきます。ここからの解説はその米軍とCarl Zeiss Jenaの内情などを絡ませて述べていきたいと思います。
◉ 1945年4月11日、Carl Zeiss Jenaの工場施設群で警戒警報が鳴り響きます。
この時、Jena市の守備に当たっていたドイツ国防軍は米軍の接近を察知し、Jena市直前に位置するザーレ川東岸に防衛戦を構築していました。さらにザーレ川を渡ってJena市に通ずる「イエナ橋」の爆破準備も整えており、進軍してくる米軍のJena市突入阻止の計画だったことが分かります。
ちなみにアドルフ・ヒトラー総統は「焦土作戦」を全軍に下命していた為、例 外なくCarl Zeiss Jenaの工場施設群も破壊命令が下されていました。それに対しCarl Zeiss Jenaの工場長、兼社長でもあるHeinz Kueppenbender (ハインツ・キュッペンベンダー) 博士は、事前にナチス政権の軍需製産大臣アルベルト・シュペーアとの良好な関係を利用して、特にCarl Zeiss Jena工場施設群と光学ガラスレンズ精製工場であるSHOTT社工場施設、及び目前のイエナ橋爆破命令阻止に奮闘していたようであり、まさに米軍侵攻、及びJena市突入1周間前と言う際どいタイミングまで、必死に努力していたことが窺えますが、実は左写真のとおり、既に主だった本社屋や工場群建物の多くは、爆撃の被害を被っており、とても稼働できる状況にはありませんでした。
外なくCarl Zeiss Jenaの工場施設群も破壊命令が下されていました。それに対しCarl Zeiss Jenaの工場長、兼社長でもあるHeinz Kueppenbender (ハインツ・キュッペンベンダー) 博士は、事前にナチス政権の軍需製産大臣アルベルト・シュペーアとの良好な関係を利用して、特にCarl Zeiss Jena工場施設群と光学ガラスレンズ精製工場であるSHOTT社工場施設、及び目前のイエナ橋爆破命令阻止に奮闘していたようであり、まさに米軍侵攻、及びJena市突入1周間前と言う際どいタイミングまで、必死に努力していたことが窺えますが、実は左写真のとおり、既に主だった本社屋や工場群建物の多くは、爆撃の被害を被っており、とても稼働できる状況にはありませんでした。
◉ 1945年4月12日、ドイツ国防軍イエナ市守備隊によりザーレ川イエナ橋爆破。
◉ 1945年4月13日、米陸軍第4装甲師団と第80歩兵師団がミュルタール渓谷を経由して、ザーレ川の渡河に成功し、イエナ市街地に突入開始。ドイツ国防軍守備隊はイエナ市東部地域に押しやられ、僅か数時間で壊滅し降伏。米軍のイエナ市占領が始まる。
◉ 1945年4月19日、キュッペンベンダー氏により再建計画が立案想起される。
これは近い将来のドイツ敗戦を予期して、数カ月間に渡る工場再建計画を起草したものであり、そこには眼鏡レンズ、カメラレンズ、精密機械光学機器の3つの柱を製産の中心に据えた、研究所と設計事務所、管理部門、業務部門などへの新規採用従業員配置などまで含んだ壮大な計画だったようです。
またこの時、キュッペンベンダー氏は、1945年の秋までに双眼鏡やライフル用照準器、測距儀などの製品を米軍に納品するとした誓約書を提出することで確約したものの、実際の米軍占領期間中のCarl Zeiss Jena工場施設群の稼働は一切行われる状況になかったようです。
◉ 1945年4月20日、戦時徴用兵3,899人を開放。
この時の開放民間人の内訳は、ロシア(26.7%)、ベルギー(23.5%)、イタリア(8.8%)、オランダ(7.8%)、チェコスロバキア(4.7%)だったようですが、残り28.5%は主にユダヤ人の囚人だったことが後に判明しており、戦後の戦犯扱いを逃れることで再建計画を実行したいが為に、伏せられていた可能性が高いようです。
◉ 1945年6月10日、科学技術文書や特殊機器を搬出開始し、第45航空補給軍によって搬送スタート。
◉ 1945年6月11日〜16日、さらに科学者と設計技師、及びその家族など1,500人以上をトラックに分乗させて移送開始。
◉ 1945年6月11日時点で、正式に米軍のイエナ市からの撤退命令が下令される。
この結果、キュッペンベンダー氏の工場再建計画は完全に頓挫します。ところが米陸軍第8師団は、既に19両の貨車に積載完了していた原ガラス材とガラス工場設備を工場に戻し始め、代わりに主要科学者(35人)、設計技師(20人)、及び重要文書を接収する命令を受託します。
◉ 1945年6月21日、米軍第12機甲師団が他に残っていた科学者や設計技師1,500人を検査開始。さらにツァイス工場従業員81名、SHOTT工場従業員41名他、イエナ大学の教授や講師、職員含む家族など500人なども1945年6月23日~25日の期間に全て移送し、ここにイエナ市からの米軍の完全撤退が完了します。
※但し、本人意志によって敢えて移送を拒否し、イエナ市に残った科学者や設計技師とその家族が相当数残っていたようです。
◉ 1945年7月1日、旧ソ連軍の将校2人がイエナ市を訪れ、市長に接見。以降旧ソ連軍に拠るCarl Zeiss Jena工場施設群とその機械設備にガラス原材料や必要人材まで含む、ほぼ全てをソ連本国に移送する接収作業が実施されました・・この接収を指して「デモンタージュ」と呼称します。
なお、米陸軍第8師団への命令が途中で変わった理由は、英国首相チャーチルと旧ソ連最高指導者スターリンによる取り決めにより、米軍占領地域とベルリン市の東西分割が交換条件として成立したことに起因するようです。
結果、旧ソ連軍による接収後に、Carl Zeiss Jenaの工場施設群に残されていた設備は、凡そ10%にも満たなかったと言う熾烈極まる状況だったようです。
このような状況から旧東ドイツ内でのCarl Zeiss Jena再建がスタートしたワケで、何よりも4月に先にイエナ市に突入していた米軍によって、その後の旧西ドイツoberkochen (オーバーコッヘン) 市でのCari Zeiss創設と、さらに商標権裁判の勝訴を決定づける人材や重要文書の接収など、戦後秩序が決まる史実へと繋がったことが分かるのです(汗)
その意味で1945年4月11日〜6月23日までの凡そ2ヶ月半に、全ての歴史が動いたと言っても良いのかも知れませんね・・。
ちなみに旧ソ連本国に移送されたCarl Zeiss Jenaの従業員が旧東ドイツに帰国できたのは、1950年代に入ってからなので、凡そ10年間前後の期間囚われの身になっていたことが分かります (もちろんそれは囚人扱いではなく技能者としての待遇を受けていた)。
※いずれも、Wolfgang Mühlfriedel (ヴォルフガング・ムーフリーデル)、Edith Hellmuth (イーディス・ヘルミュート)・・共著「Carl Zeiss Jena 1945 – 1990」より
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●